

![]() 1993年に独立したスロバキア
1993年に独立したスロバキア
2002年の夏休みに東ヨーロッパへ行きました。わずか8日間、日本への往復を除けば正味5日間でハンガリー・スロバキア・オーストリア・チェコの4ヶ国をまわる駆け足旅行です。ベルリンの壁の崩壊から13年が経過し、東欧諸国の中でも変化の激しいハンガリーとチェコですが、まだまだ西ヨーロッパとはひと味違う部分も残っていました。
ハンガリーの首都ブダペストはこちらから。
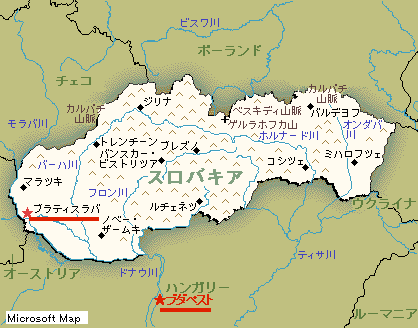
ヨーロッパの中東部に位置するるスロバキア共和国は、北でポーランド、東でウクライナ、南でハンガリー、西でオーストリアとチェコに接する 内陸の国です。かつてはチェコスロバキアとしてチェコと連邦を形成していましたが、ベルリンの壁崩壊以後の民主化の過程で 路線の違いが顕著になり、1993年1月1日にチェコと分離して独立しました。
面積は北海道の約半分の、人口は北海道なみの500万人余りの国です。首都は国の西端に位置する人口45万人程度の古都ブラチスラバです。
※ 2ページの末尾にそれぞれリンク先を設けました。詳しく知りたい方はご利用ください。
![]() ドナウ川の水門
ドナウ川の水門
ハンガリーの首都ブダペストを出発したオーストリアのウイーン行きの水中翼船はドナウ 川を高速でさかのぼります。3時間余り経過して川の風景にも飽きてきたころ、水門に到着します。ドナウ川には水位を調節するために数カ所の水門が設けられており、ここもそのうちの1個所です。川の下流側と上流側にそれぞれ大きな扉が設置されており、川をさかのぼる船は、まず開いている下流側の扉をくぐって水門に入ります。
 |
 |
| 水門の下流側 側壁の黒くぬれている部分まで水を注入する | 水位が上昇して上流側の水門の向こうが見えてきた |
航走中は外に出られない水中翼船ですが、水門に入って停船すると後部扉から階段を伝って屋上に出られます。川をさかのぼる何隻もの船が水門の側壁に寄り添って停船すると、水門の上から大勢の見物客が見守る中、下流側の扉が閉まり注水が始まります。
高低差は30m程度でしょうか。水門の底面から注水されているようで、水面がゆっくりと上昇し船は持ち上げられていきます。やがて上流側の水面と同じ高さになると上流側の扉が開き、水中翼船は再び航走を開始します。
上流側は水門でせき止められた水で川幅が広がり、湖のようになっていました。
![]() 首都ブラチスラバの市電
首都ブラチスラバの市電
水門から1時間、ブダペストを出てから4時間半で、大きな街が見えてくるとスロバキアの首都ブラチスラバです。水中翼船は速度を落としてオソブニー桟橋に接岸します。ここで、全体の3分の1程度の乗客が下船しました。
浮き桟橋から歩いて川岸の小さなターミナルビルにある入国管理の事務所に向かいます。川から入国するのは初めての経験です。空港と同様に、バスポートをチェックして入国スタンプを押してくれました。
 |
 |
| ブラチスラバの桟橋とブダペスト発ウイーン行き水中翼船 | 桟橋近くの単線の線路を走る新型の連接車 |
ブラチスラバではドナウ川は西から東に流れ、市街地はその北側に広がっています。桟橋付近は旧市街地に近く、建物を出ると目の前の通りの真ん中には単線の線路があり、路面電車が走っています。ここの電車は一方通行のようで、川に沿って少し西へ歩いて旧市街の入り口付近まで来るとポイントで線路が分かれており、複線になっています。
 |
 |
| 停留所安全地帯と旧型の連接車 | 片運転台のため電車の後部はこんなスタイル |
電車は大きなパンタグラフをあげた2両編成または2車体連接車で、朱色とクリーム色に塗り分けた丸いタトラカーです。チェコスロバキア当時にプラハで製造された、共産圏の標準型路面電車です。連接車は、ここで初めて見かけました。
朱色に窓まわりが紺色でシングルアームのパンタグラフをかかげ、正面の窓を大きくして方向幕をその中に取り込んだ新型の連接車もいます。正面から見るとモダンなスタイルですが、側面は相変わらずの丸いタイプ。スロバキアとして分離独立後のタトラカーの新車だと思いますが、ドイツやフランスのLRTに比べると野暮ったさを感じます。西ヨーロッパでは主流となっている低床車は、ブラチスラバでは見かけませんでした。